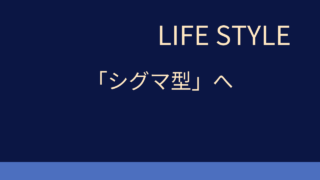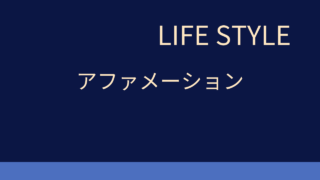今回は様々なカテゴリーのGKを指導する際に、
私が意識していることを記事にしてみたいと思います!
みなさんも日々のトレーニングでカテゴリーを問わず、
「どうやってポイントを伝えようか」
「この戦術を落とし込むにはどうやったらいいのか」
という悩みは必ずあると思います。
そこで、今回は私自身が日々のトレーニングを構築する上で、
意識しているポイントを書いていきたいと思いますので、
ぜひ読んでみてください!!
1.「M-P-T-M」で考える『岡田メソッド』から
不変の原則であるプレーモデルと試合をつねに比べて、
問題があったところをトレーニングします。(中略)すなわち、M-P-T-M(マッチ、プレーモデル、トレーニング、マッチ)と考えています。
岡田武史『岡田メソッド-自立する選手、自律する組織をつくる16歳までのサッカー指導体系』 英治出版株式会社、P.186
早速、引用から始まりますが、これが本当に大切なポイント!
こちらはJFAの「M-T-M理論」というものから、
発展されたもの。
試合のなかで、改善点をみつけ、トレーニングをする。そして、また試合に臨むというサイクルの話だけではありません。
特に、近年では単純なテクニックというものだけではなく、ゲームやプレーの大枠を抑える「プレーモデル」というものが、誕生しています。
※余談ですが、私もGKにおけるプレーモデルは作成しておりますので、
そちらも記事にしてみたいと思います!
話をもどして、GKトレーニングに限らず、トレーニングは試合を想定されていなければならないと思います。
そのため、ゲームのシーンを切り取り、分析。
その分析する際の基準として、プレーモデルを使うということですね。
毎回指導者が言っていることが変わったりすると、選手も困惑します。
また、チーム(組織)としての脆弱性もありますね
しかし、毎回そのシーンが来るとは限らないのも、サッカーの分からない複雑なところ。
なので、まずは
「ボールがここにあるときは、こういうプレーをする」
という大枠が必要だと思います。
このラインより上のエリアが無料で表示されます。
2.FPとの兼ね合いを考慮する
ゲームでの失点や改善点を、
私はなるべくGKだけで解決させ続けないように努めています。
テクニックの部分は各自フィードバックで対応可能。
しかし、ゴールを守る(ゴール・ディフェンス)ことやスペースを守る(スペース・ディフェンス)ことなど、GKだけで守れないことも多々あります。
話は変わりますが、みなさんはペナルティーエリアやゴールの幅、
PKマークの位置など、具体的に言えますか?
ドキッとされた現役選手や指導者の方々もいらっしゃるかもしれませんが、GKにとって、非常に重要な要素になります。
コートの大きさや、ゴールの大きさは誤差はあるかもしれませんが、ほとんど変わらないものです。
それを基準にポジションの感覚を掴むということも良くありました。
しかし、対戦するチームやスタイル、味方の配置やシチュエーションなどは、挙げだすとキリがありません。
なので、守備の選手(DF)や中盤(MF)の選手たちとコミュニケーションをとることが大切かと思います。
自分がGKとしてゴールを守るために、味方にやってほしことをしっかり伝える必要があるんですね。
-ToDo- 具体的に何からしていけばよいのか?
まずは、「言語化」ではないでしょうか!!
ちなみにそれはこのような流れで作りました。
- 自分が考えるGKの理想像
3つぐらいの要素に絞る - シチュエーションごとの整理
シュートストップやクロスなど、GKのプレーをそれぞれ分類していく - そのシチュエーションにおける守り方を言語化していく
※多すぎず、少なすぎず - 「いつ、どこで、どのように」を明確にしていく
- 共通する要素をピックアップして、まとめる
このような手順を踏めば、
いいものが出来上がるかと思います!
しかし、これらはGKを経験したり、
指導をしたりする人でも苦戦することがあります、、、
※作成や相談などのサポートはオンラインでも別途対応できるように、検討中ですので、ここまで読まれた方はコメントください。
これらが完成すると、選手たちのフィードバックにも影響しますし、
特に振り返りがかなり楽になりますね!!
選手たちも指導者が求めるものが明確になります。
シーンごとの守り方はまた、別の記事で紹介するとして、
今回はここまでにしたいと思います!!